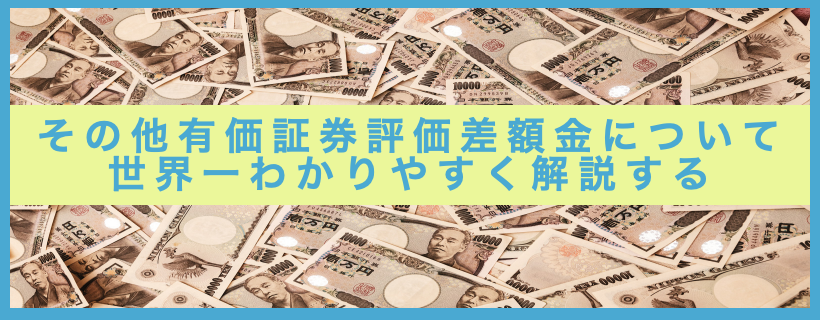
結論:ただの評価差額
いきなりですが、こちらが今回の結論です。
文字数も多く、複雑そうな名前ですが、結局は評価差額を表しています。
「その他有価証券評価差額金」とは、会社が所有する有価証券についての損益を表す(厳密には違いますが)勘定科目です。
そもそも、財務諸表に表示される有価証券には4種類あります。
- 売買目的有価証券
- 満期保有目的債券
- その他有価証券(投資有価証券)
- 自己株式
それぞれがどのようなものかは別項で解説しますが、「その他有価証券評価差額金」はその他有価証券に関連する勘定科目です。
そして、「その他有価証券評価差額金」は、期末にその他有価証券の時価を求めて、それが取得価額より大きいか小さいかを表します。
これを仕訳で表すとこうなります。(法定実効税率40%と仮定)
時価が取得原価を1,000上回る場合
投資有価証券 1,000 / その他有価証券評価差額金 600
/ 繰延税金負債 400
という仕訳になります。
時価が取得原価を1,000下回る場合
その他有価証券評価差額金 600 / 投資有価証券 1,000
繰延税金資産 400
という仕訳になります。
※繰延税金資産・繰延税金負債は一旦スルーしましょう。
見ていただくとわかる通り、それぞれの場合に共通して、投資有価証券という資産勘定に対応するようにその他有価証券評価差額金勘定を立てています。
仕訳は上記のもの以外出てこないので、単純に投資有価証券という資産勘定を増やすのか減らすのかで貸借を切り替え、
相手勘定にその他有価証券評価差額金と繰延税金資産/負債(金額は法定実効税率、貸借で判断すればOK)を持ってくるだけです。
損益としては認識しない
ここからが本題ですが、今回覚えてほしいことは、
その他有価証券評価差額金という勘定は費用でも収益でもなく、純資産勘定に分類されるということです。
そして、税効果会計が適用される(繰延税金勘定)理由もここにあります。
そもそもその他有価証券とはどのようなものでしょうか。
たとえば株式のように価格変動による収益を狙った売買目的のものは売買目的有価証券に分類されますし、社債のように満期を迎えるまで利息をもらうために持っておくものは満期保有目的債券に分類されます。そして、その他有価証券は、その名の通りそれ以外のものです。
それ以外のもの。
売買目的でも、満期保有目的でもないもの。
一般的には企業間の持ち合い株式などが該当します。
繰り返しますが、売買目的ではないので、いちいち期末に評価損益を認識して帳簿価額を更新する必要はありません。(というより認められていません)
でも、簿価は時価に合わせる必要があるんです。
いくら売買目的のものではないと言っても、財務諸表に何年も前の古い取得価額がそのまま載っている状態ではさすがに投資家の判断を誤らせることが懸念されるためです。
そこで出てくるのが、評価差額をどう会計に反映させるかという問題ですよね。
帳簿価額を変えるということは、その辻褄をどこかで合わせないといけない。
売買目的有価証券であれば、時価を反映させる際に評価損益を相手勘定として認識できるわけですが、
売買目的ではないものの評価差額を損益として認識するわけにもいかない。
となってくると、、、
そう、純資産です。
会社の利益を増減させる損益項目には算入させず、あくまでB/S上で完結する純資産項目にするわけです。
投資有価証券の金額が増えれば、その他有価証券評価差額金という純資産が増加し、投資有価証券の金額が減れば、減少する。
こうすれば、売買目的でないその他有価証券の差額を損益に算入させなくて済みます。
そして、期末の帳簿価額も時価に即した実体のある金額にすることができます。
一件落着ですね。
その他有価証券評価差額金をもっと知るためにおすすめの本
ここで、一冊本を紹介したいと思います。
今回は、その他有価証券評価差額金を取り上げて、会計上の扱いについて解説しましたが、
サラリーマンの方や経営者の方、会計に関して学習している人におすすめなのがこちら。
財務諸表の見方
日本経済新聞出版
Amazon価格:941円
損益計算書、貸借対照表などの財務諸表に記載される項目について、それぞれが何を表しているのかを、
会計の専門用語ではなく意味合いや目的をもとに解説している本です。
筆者は大学でも会計学の研究をしていて普通の人よりは知識があるんですが、それでもどうしてもかたい言葉が多くて理解しにくいのが会計なんですね。
そんな僕がこの本を初めて読んだ時、難しい言葉を使わずわかりやすい言葉で会計を解説しているこの本を在学中に読めていたら・・・と心から残念に感じました。
ちなみに、今回取り上げた「その他有価証券評価差額金」についてもばっちり解説されています。
わかりやすく会計について知ることができるので、
今まで、会社を見る上で会計の知識は必要とは思っていたけどいまいちとっつきにくい・・なんて感じていた方にはうってつけの一冊です。
ぜひ、みなさんもこれを機に知識を蓄えてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、「その他有価証券評価差額金」って名前長くないですか?手書きで仕訳かくのすごい苦労したな・・・
.png)


