身の回りには意外な数え方がいっぱい
皆さんの身の回りには、そのイメージとはかけ離れた数え方をするものがあります。
有名なところでは、蝶やタンスといったところでしょうか。
ものの数え方は、正確にいうと助数詞と呼びます。
一つ、二つ、一個、二個と汎用的に呼んでしまえばそれまでですが、これも日本特有の大切な文化の一つですよね。
そんな、知っておくと明日から自慢できるかもしれない、意外なものの数え方について今回は解説します。
意外な数え方
蝶の数え方
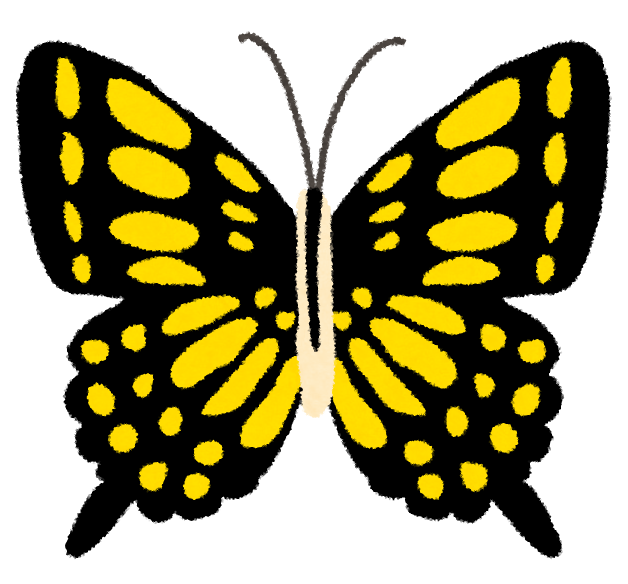
「〜頭」
意外な数え方をするものとしては、結構メジャーなものが蝶ですね。
「〜頭」と数えるもののイメージとしては、なんだか大きくて頑丈そうな生き物に対し使われそうですが、蝶も一頭、二頭といった数え方をします。
タンスの数え方
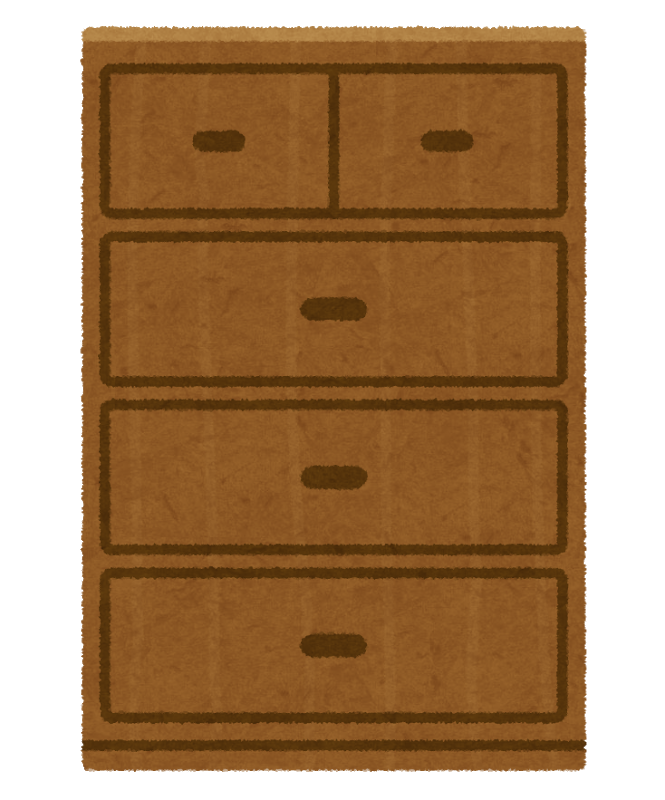
「〜棹(さお)」
タンスは一棹、二棹といった数え方をします。
昔、大火があり多くの家財道具を運び出すときに、竿を通して持ち運べるような構造にしたことからこの数え方が生まれました。
イカの数え方
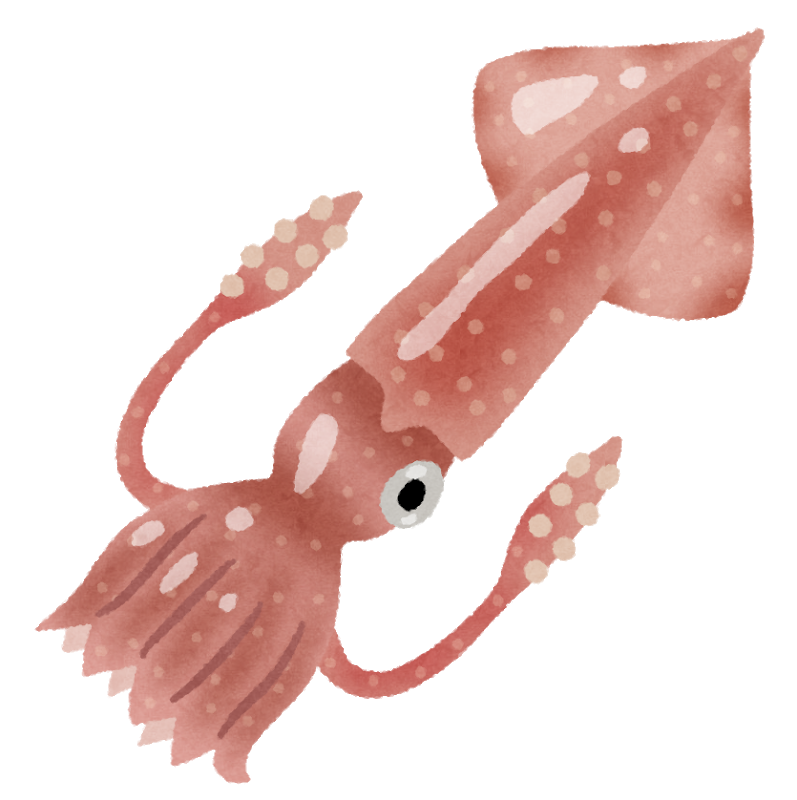
「〜杯」
イカは、一杯、二杯といった数え方をします。
魚を数えるときにも、一尾、二尾と少々独特な数え方がありますが、それをも凌ぐ特殊性には脱帽です。
ちなみにカニも同じく一杯、二杯と数えます。
テーブルの上に一杯のビールと一杯のイカがある、なんて不思議な響きですね。
余談でした。すみません。
ウサギの数え方
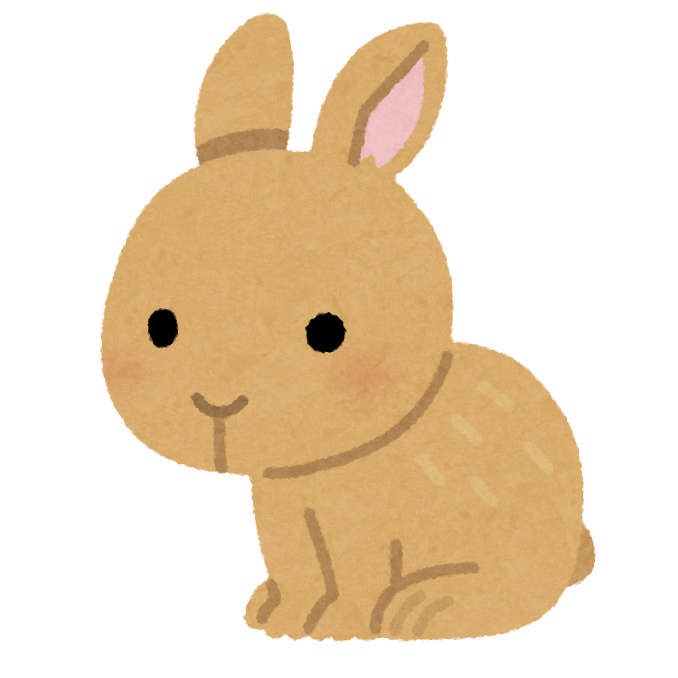
「〜羽」
うさぎは、一羽、二羽といった数え方をします。
意外な数え方界では割とメジャーなものな気はしますが、明らかに鳥ではないし羽も見当たらないのに一羽、二羽と数えるのはやっぱり不思議な感じがしますね。
ウニの数え方
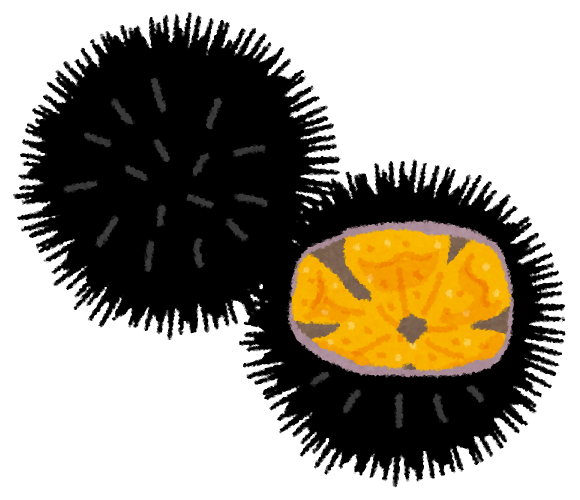
「〜壺」
ウニは、一壺、二壺といった数え方をします、
生き物については〜匹や〜頭で数えるもの、という常識が通用しなくなってくる気がしますね。
かなり意外な数え方ではないでしょうか。
ちなみに、一壺、二壺、といった数え方をするのは殻に包まれた状態のウニだけで、剥いた身を数える場合は普通に一つ、二つと数えます。
山の数え方
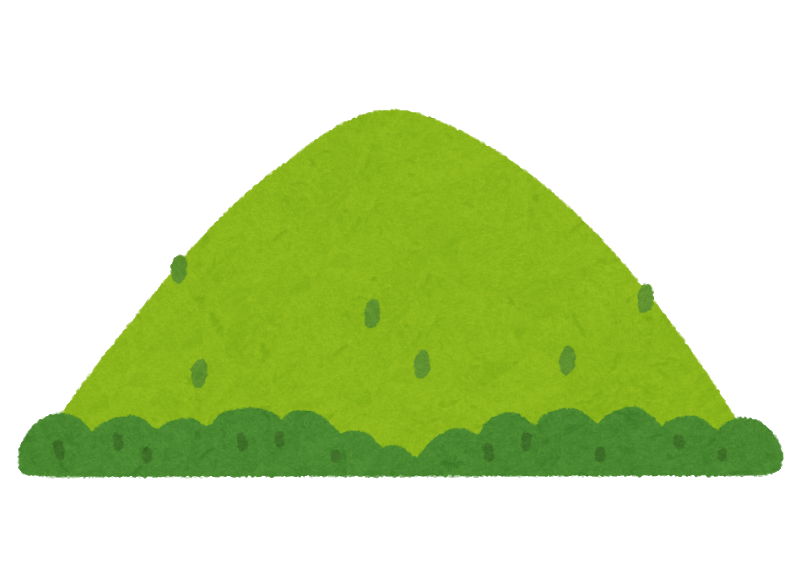
「〜座」
山は、一座、二座といった数え方をします。
昔の人は、山には神様が宿ると考えたため、敬意を表してこのような数え方になったと言われています。
お守り、絵馬の数え方

「〜体」
お守りは一体、二体といった数え方をします。
こちらも山の数え方と同様に、お守りには神様が宿っていると考えてられてきたためこのような数え方になったようですね。